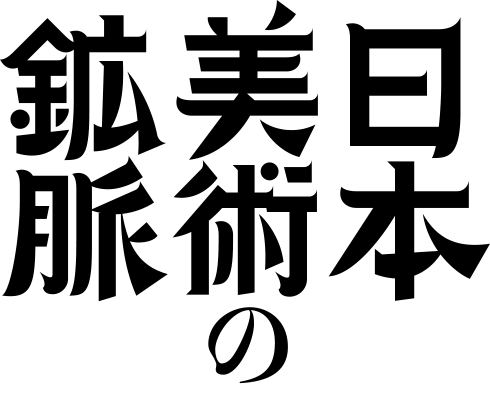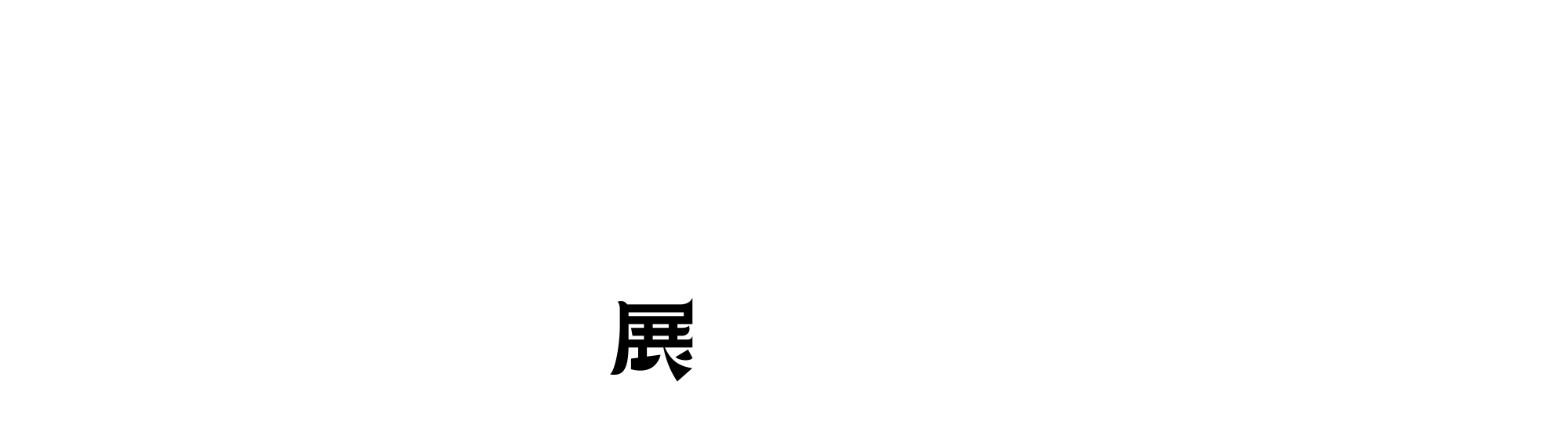
監修にあたって
近年、「日本美術ブーム」ともいうべき状況が続いています。かつては、西洋美術に比べて人気がなかった日本美術。しかし、世紀の変わり目あたりから状況は徐々に変わってきました。そんな「日本美術ブーム」を牽引してきたのは、間違いなく江戸時代の画家、伊藤若冲(1716~1800)です。2000年に京都国立博物館で開催された「没後200年 特別展 若冲」をきっかけとして、空前の「若冲ブーム」が巻き起こり、2016年に東京都美術館で開催された「生誕300年記念 若冲」展には、なんと46万人もの観客が詰めかけたのです。しかし、そんな若冲も、2000年以前には一般の人々にとっては日本美術の「知られざる鉱脈」でした。
2000年代以降、有名な作品が数多く展示されるような日本美術の展覧会には、何十万人もが詰めかけるようになりました。コロナ禍が終息した今後、日本美術に対する注目度はますます高まっていき、国宝、重要文化財などを多数展示する展覧会が続々と企画されています。しかし、この「日本美術の鉱脈展 未来の国宝を探せ!」は、すでによく知られた作品を呼び物として企画するものではありません。これまでほとんど注目されていないもの、一部の研究者は熱心に研究しているものの、一般の方々にはほとんど知られていないものなど、「知られざる鉱脈」としての日本美術を、多くの人々に観ていただきたいという思いで企画した展覧会です。
縄文から現代まで、出品作の時代、ジャンルは多岐に及びます。たとえば、縄文土器。ようやく1990年代からいくつかが国宝指定されましたが、ほかにも指定されるべき作品はたくさんあります。室町時代の絵画にも、一般には知られていないものの、きわめて個性的で魅力的な作品があります。そして、江戸時代の絵画は、若冲をはじめとする「奇想の画家」の発掘はずいぶん進みましたが、それでもまだほとんど知名度がない素晴らしい作品が多数あります。さらに、明治時代以降の絵画、工芸には、「知られざる鉱脈」がたくさん眠っています。
その鉱脈を掘り起こし、多くの方に見ていただき、観客の方々がご自分の眼で「未来の国宝」を探していただきたいという思いで、この展覧会を企画しました。大阪・関西万博が開催される2025年。その機会に、さらに多くの人々に日本美術の魅力を発信したいと考えています。
山下裕二(本展監修者、明治学院大学教授)